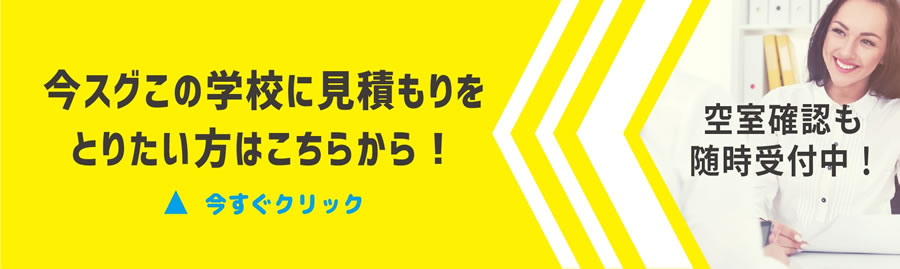すれ違う留学生や欧米の観光客にストリートチルドレン。大人から子どもまで全力で喜怒哀楽を表現し、バスケットボールに熱中する人々。そしてレチョン(フィリピンの代表的料理で豚の丸焼きにしたもの)になってしまいそうな燃える日差し。
これが当時、くたびれたTシャツに30Lのバックパックを背負った大学生の僕が見たフィリピンの印象だった。

今、僕の知るフィリピンとはちょっと違ったフィリピンが眼前に広がっている。
ここは、バギオ。
街ゆく人は見慣れた半裸や半袖ではなく、重ね着をしている。話しかけてみると、この国の人たちにしては珍しく、すこしシャイだ。何より違うのは、ここには海がない。目につくのは緑色ばかり。
調べて知っていた情報としてのバギオは、約40万人(※セブの約3分の1)気候は乾季と雨季にわかれ、気温は最高26℃、最低14℃といったところ。しかし、実際に暮らしてみて感じるこの街の魅力は、PCで得られる数字や言語化しやすい情報にはないことに気付いた。
山岳地帯の入り口に位置するため、山岳民族の文化にマニラに象徴される先進的な文化が混ざり合い、米国が戦時中に作った都市というだけあって、欧米の香りも残っている。さらにそこに、近年では英語の語学学校を多く有するという理由で日韓の文化が交差している。そんな独特の雰囲気に魅せられてフィリピン中から有名な芸術家が集まったり、独特の感性を持った日本人が住んでいたりもする。戦前に日本人が移住してインフラを整えた歴史も興味深い。

24歳、新卒で入社後2年間勤めていた東京の商社を退職すると同時に、17年間続けたバスケットボールからも引退した。正直なところ、当時の仕事にも実業団での選手生活にも一切不満はなかった。
退職の理由は就職活動の面接で滞りなく口から出た、嘘か誠か自分でさえ分からない言葉たちのように立派でも整合性のあるものでもなく、何となくというものだった。ただ、それが自分にとっては、とてもに自然な流れに感じられた。
周りが心配してくれた職を失うことよりも、人格形成の大部分を担った競技生活から離れることの方が、僕にとっては大きかったと思う。
2年目のある日、担当していた企業が籍を置く山手線の大崎駅南口改札で、ふいに思い浮かべた地図が日本列島だったときには衝撃を受けた。いつも頭に描く地図は歴史や旅好きだったこともあり、幼少期からずっと世界地図だったからだ。「日本なんて狭い」という思い上がりではなく、自分の中の当たり前が自分でも知らないうちに日々の何気ない暮らしの中で変化してしまうことがある、という事実に驚いたのだと思う。
もう1つは、その数ヶ月後に取引先の工場のある石巻を訪れたときのこと。取引先の引率の方が「工場訪問の前に連れて行きたいところがある」と、案内してくれた高台は僕が19歳の時に汚れたパーカーを着て野宿をしながら旅をして辿り着き、ボランティアという言葉に自分なりの解釈も持たずに参加し、ただ呆然と3.11の爪痕を目に焼き付けた場所だった。
思わぬ形で再訪したその高台で、オーダーメイドで仕立てた何万円もするスーツを着て立っていること、明日には東京で家賃10万円の小綺麗な部屋が帰りを待っていることに、強烈な違和感を感じたのを覚えている。
違和感の正体がなんだったのかはさておき、未だにそこには広大な更地と架設住宅、あの時の爪痕が深く残っていた。もちろん、その後の工場見学の内容は覚えていない。

退職後にフィリピン行くことを決めて、準備のため桜の咲く故郷に帰ると、97歳になる祖父がベッドから起き上がることができなくなっていた。正月の帰省では一緒にビールを飲んだ記憶がある。たった3ヶ月。
昔、祖父が大切に保管していた特攻隊の仲間の遺書の写しを見せてもらったことがある。戦時中に見聞きしたフィリピンに関する話も聞かせてくれた。
零戦の整備士として様々な土地を経験し、敗戦直後は現在の北朝鮮である元山の収容所で捕虜となり、地獄のような日々に耐え抜いたのち、生きて自力で祖国に帰ってきた祖父。戦火をくぐり抜け、1世紀近くを力強く燃えた命の火が消えかかろうとしているとき、その目に今の僕や日本はどう映っているのだろうか。
そんなことを考えながら、着陸態勢に入った飛行機から祖父の整備した零戦が舞っていたフィリピンの空を眺めた。

今、僕と祖父の知るフィリピンとはちょっと違ったフィリピンが眼前に広がっている。
ここは、バギオ。
大きな事件はほとんどない平和な街。ありえないほど近くでなる雷、東南アジア特有の臭いを乗せているにもかかわらず涼しい風、意味もなく人が集まり笑うバーハムパーク、好奇の目で見られるローカルのジム、おしゃれの集うセッションロード、毎日「what’s up!!」と声をかけてくるトランスジェンダーの屋台の店員に、旅で訪れたどの国のよりもふくよかな野良犬野良猫、4000円程度で買える偽物のバスケットボールシューズ。
そのどれもがきて良かったと思わせてくれる魅力を持っているし、再出発するのに適した土地だといえる条件も揃っている。一方で、どこに行こうが自分次第だという使い古された言葉を再認識した土地でもある。そんな風に思わせてくれる高い志を持った人たちに、ここでたくさん出会ったからだ。

再出発などと偉そうなことを書いたが全てを脱ぎ捨てた気は毛頭ない。今までにもらった縁と恩が僕の武器だ。これを循環させていきたいと思う。企画編集とライターとして携わらせていただいているこのメディアの仕事もバスケと旅の縁が元々のきっかけである。
たとえきっかけは何となくだとしても、厳しい山岳地帯を切り拓いてバギオが栄える要因となったケノンロードを作った戦前の日本人のように、分かれ道を選ぶのではなく進んだ跡が道になるような生き方をしていこうと、切に想う。
あとがき
個人としてまっさらな状態で感じたバギオの第一印象とここにたどり着くまでをとりとめもなく書きました。フィピピンやバギオ、そして自分に興味を持ってくれる方がいらっしゃれば、幸いです。
また、この文章が自分にとっても誰かにとっても答えではなく、問いになればと思います。

 >
>